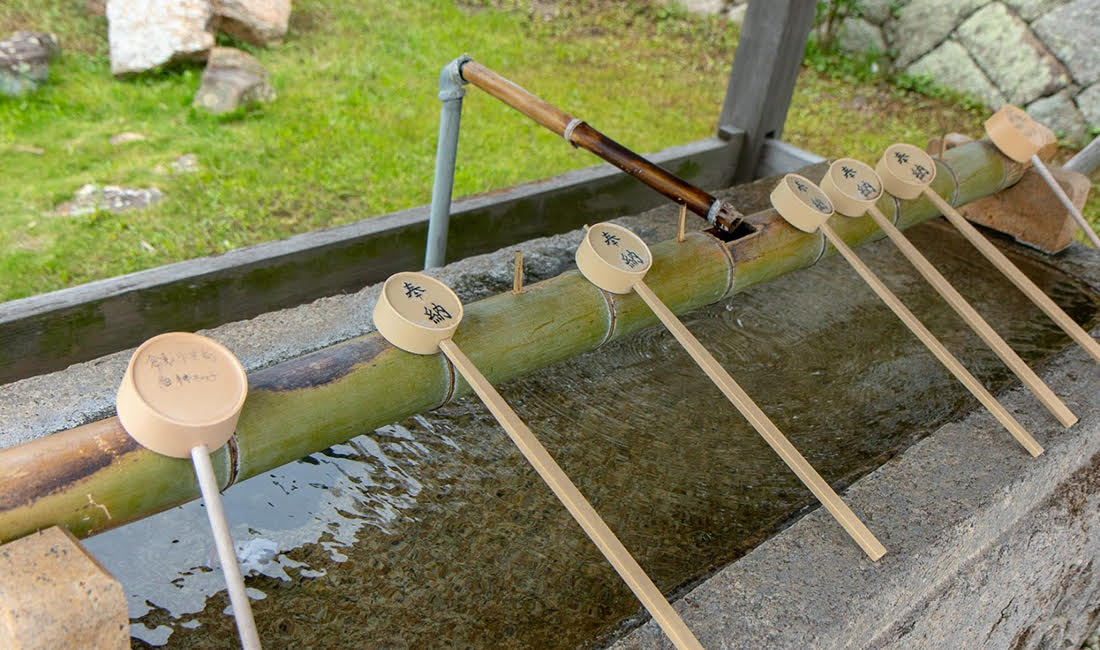岩屋神社の基本情報
- 住所
- 兵庫県淡路市岩屋799
- アクセス
- JR山陽本線明石駅下車、徒歩7分明石港から淡路ジェノバライン13分、岩屋港下船徒歩6分
- 駐車場
- あり
- 詰め所
- あり(時々有人)
岩屋神社のご由来
ご祭神は、国常立尊(くにのとこたち)・伊弉諾命(いざなぎ)・伊弉冉命(いざなみ)の3柱です。
神社創建は不明で関連する恵比寿神社との調査によると、淡路島では最も古い神社だということがわかっています。
岩屋神社は、淡路島岩屋の氏神さまで、天地大明神と言われて町の人から非常に崇敬があついです。
岩屋神社は、第10代崇神天皇(紀元前93年~30年)時代には三対山(城山)に鎮座されていました。
古事記や日本書紀でも語られてる『神功皇后の三韓征伐』の際には風や波を避けるために垂水の浜から岩屋に渡られて岩屋神社で戦勝祈願をされました。
その時に「いざなぎやいざなみ渡る春の日にいかに石屋の神ならば神」と神功皇后が歌うと波風が穏やかになったと言われています。
戦に勝利して朝鮮半島から戻られた神功皇后には、再び岩屋神社に詣られたと伝わっています。
1168年には、第78代 二条天皇によって『天地大明神』と称され、神階を上げて神供田を寄進されました。
戦国時代の1510年には大内義興が足利義稙に付き従って京都に入る前に岩屋に軍を進め、三対山に城を築きました。
その時に現在の場所に社殿を移しています。
1610年には、池田輝正が淡路を領地とした時に社殿が再興されました。
1973年2月に郷社に列せらています。
淡路島の対岸にある明石市の岩屋神社は、淡路島にある岩屋神社の分身だと古くから伝わっております。
浦祈祷祈願祭・浜芝居
「浦祈祷祈願祭・浜芝居」は3月第2日曜日に一年の豊作・豊漁を祈願する石屋神社の祭礼です。
淡路島 岩屋ならではの浜の祭りです。
午前中はえびす様と神輿を乗せた漁船が海上を行進、五穀豊穣と大漁を祈願して、鯛を放流します。
午後には、石屋神社で恵比須舞という豊漁を祈願する浜芝居が繰り広げられます。芝居の中で、えびす様が鯛を釣上げる場面は必見です。
恵比須舞のお話は、狩衣を着たえびす神が、釣竿を担いで庄屋さんの家を訪れます。
三こんの盃を飲み干したえびす神は、自分の生まれや福の神であることを話しながら舞い始め、豊漁、豊作、世界平和を祈りながら御神酒を飲み、その地に幸福を運んできます。酔ったえびす様は舟に乗り、沖に出て大きな鯛を釣り、目出度し目出度しと舞い納める、というものです。
岩屋神社の主な祭事
浦祈祷祈願祭・浜芝居----毎年3月第2日曜日開催
春祭り----毎年5月第2土・日曜日
秋祭り----毎年9月第2土・日曜日
清水 宏積

- 和風デザイン制作 ひだちデザインで神社などのホームページを制作するWEBデザイナー。
日本の神様辞典でもライター活動を行っています。
YAT

- YAT(ヤット)といいます。フリーランスのWebデザイナーで、Rish-Designという屋号で活動しています。
また、Webサイトの制作やデザインに関するブログYATのblogを運営しています。
twitter
instagram
flickr